|
現在、茨木市在住です。地理的に可能な範囲で、ご希望があれば音楽の学習のお手伝いをさせていただきます。
学校の教科の中で「体育だけが苦手」という人がいるように、「音楽だけが苦手」というお子さんも少なくありません。音楽の得意・不得意に男女差があるのか?という質問もよく耳にしますが、それよりも「どんな経験を積んできたか」「どんなふうに音楽にふれてきたか」が大きく影響しているように思います。
こんなお手伝いが可能です:
-
笛(リコーダー)、歌、ピアニカの練習
-
中間・期末テスト対策(筆記・実技)
-
音楽理論・楽譜の読み方のサポート
-
作曲の宿題(夏休みなど)
-
バンド活動のコードや聴音の基礎
-
小学校の音楽クラブでの準備・練習
-
音楽会・発表会前の対策練習
「お子さんの「できた!」の気持ちを育てるお手伝いができたらと思っています。興味のある方は、お気軽にご相談ください。
教員志望の方で、pianoが弾けるようになりたい、という方
「できること」から始めよう
-
歌が苦手?:声が小さくてもOK。ハミングや口パクからスタート。
-
ピアノが苦手?:まずは指一本でOK。ドレミの場所を覚えることから始めよう。
-
楽譜が苦手?:耳コピーに自信があるなら、それを活かして。J-POPの一部分を音で当てるゲームもおすすめ。
「これは得意かも!」と思える体験が、自信とモチベーションにつながります。
おおすみ かおり
連絡先 大墨 薫
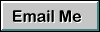
音楽が苦手? それでも楽しめる場面はたくさんあります
一般に、「男子は音楽が苦手」というイメージを持たれることがあります。それは、ピアノを弾けるかどうかが、音楽の授業での評価に関わる場面が多く、ピアノが“女子の習い事”として広まってきた背景があるからかもしれません。
ですが、ギター、ベース、ドラムが得意な男子もたくさんいますよね。ですから、学校生活や音楽の授業の中にも、ギター・ベース・ドラムを演奏・発表する場面がもっとあってもよいと感じています。
音楽会 ─ 多人数の中に溶け込む?それともリズム楽器で挑戦する?
小学校の音楽会では、器楽合奏が定番です。「演奏が苦手」と感じている子には、リコーダーや鍵盤ハーモニカなど、基本的なパートをおすすめします。うまく演奏できる子に助けてもらいながら、音楽に自然と馴染める経験ができます。
低音部で動きの少ないパートか、高音部でメロディを担当するかは、子ども自身の「好き」に任せていいと思います。
反対に、自信のある子や「注目されたい!」という子には、パーカッション、木琴、鉄琴、ピアノ、アコーディオンなどもおすすめです。
特にリズム楽器(タンブリン、カスタネット、鈴、トライアングル、ウッドブロックなど)は一見簡単そうに見えますが、リズムの正確さが求められ、実は注目されやすいパートです。
パーカッションの中で取り組みやすいのは?
大太鼓(バスドラム)は比較的取り組みやすいです。
よくあるパターンは:
逆に、小太鼓やタンブリンは裏拍(拍と拍の間)を叩くため、難しく感じるかもしれません。
最近の音楽会を見ていると、パーカッションに挑戦している男子も多く、ピアニカを上手に弾いている男子もいます。
(ちなみに筆者は、パーカッション、とくに裏拍が苦手で、これまであまり関わってこなかったパートです…)
音楽会の思い出をそっと残したい方へ
お子さんの音楽会をそっと撮影したい方には、ペン型ビデオカメラなどもあります。自然な形で記録に残したい方に便利です。
大学生になって初めてオーケストラに挑戦!
大学入学後、受験が終わってから初めて「オーケストラ部に入ってみよう」と思う人もいますよね。ただ、中学から吹奏楽部で活動していた人や、子どもの頃から弦楽器をやっていた人も多く、経験者が多いのが現実。
初心者の多くは セカンド・ヴァイオリンに入ります。ここは、初心者と、それをサポートする上級生で構成されることが多いです。中には、理系で忙しい学生が「比較的負担が少ないから」と選ぶこともあるとか。
また、体格に恵まれていれば、チェロのように低音部で動きの少ない楽器を選ぶのもおすすめです。大人になってからチェロを始める人も、実はたくさんいます。
こうしたお話が、音楽に対してちょっと自信がない人にも、「やってみようかな」と思ってもらえるきっかけになればうれしいです。
小学校の音楽会 ── 今と昔
学校によっても違いはありますが、昭和40年代の小学校の音楽会といえば、文部省唱歌を歌ったり演奏したりすることが中心でした。器楽合奏では、行進曲(マーチ)や、比較的リズムの簡単なクラシック音楽が多かったように思います。
当時の音楽教科書も、やはり文部省唱歌が中心で構成されていました。音楽会では「標準服(制服とは別)」を着て、全員が紺色の服で壇上に立ち、整然と並びました。他には、PTAのコーラスや音楽部の発表などもありました。
中学校の文化祭では、先生たちの合唱(職員合唱)も名物でした。先生方が壇上にずらりと並ぶと、生徒からは「お?!」と冷やかしの声が上がったのも、懐かしい思い出です。
男子の音楽参加は?
今でも小学校の音楽クラブでは男子が少ないかもしれませんが、昭和40年代は、さらに男子の参加率が低く、全くいないという学校も珍しくありませんでした。
ある年、男子が3人だけ参加していた音楽会では、その3人が「上・中・下」とボタンのように壇上の中央に並び、「荒城の月」を歌っていました。「男子が3人も出てるなんて、立派な学校だ」と、感心する声もあったほどです。
(筆者が小3まで在籍し、転校後に訪れた安井小学校での実話です。)
音楽会が"SHOW"に変わった今
時代が変わり、今の音楽会は“ショー的要素”が強くなってきています。衣装をそろえたり、ダンスを取り入れたり、選曲もテレビ主題歌やポップス、創作音楽など、よりバリエーション豊かになっています。
たとえば「雨」をテーマにして自分たちで曲を作り、手作りの楽器で演奏する、というような試みも見られます。
一方で、昔の文部省唱歌は、現代の価値観に合わないとして教科書から削除されたものもありますが、逆に、懐かしの唱歌を味わおうという中高年向けの講座なども人気を集めています。
撮影は…禁止の学校も増えています
最近の小学校では、音楽会や授業参観での撮影を全面的に禁止しているところも少なくありません。児童が見回りをして注意するという学校もあります。
音楽会では、専門の写真業者が撮影し、後日注文できる仕組みになっている場合がほとんどです。
それでも「どうしても我が子の姿を記録したい…」という保護者の声も。そんなときには、目立たないペン型ビデオカメラという選択肢もあるようです。見た目は普通の黒いボールペン。ちょっとした「記録」に役立つかもしれません。
筆者自身、昭和の音楽会や授業、小学校の雰囲気がとても懐かしく、少しも嫌いではありません。今のようにカラフルでにぎやかな音楽会も素晴らしいですが、昔の素朴な音楽会にも、また違ったよさがありました。
http://www.kididdles.com/ |


![]()